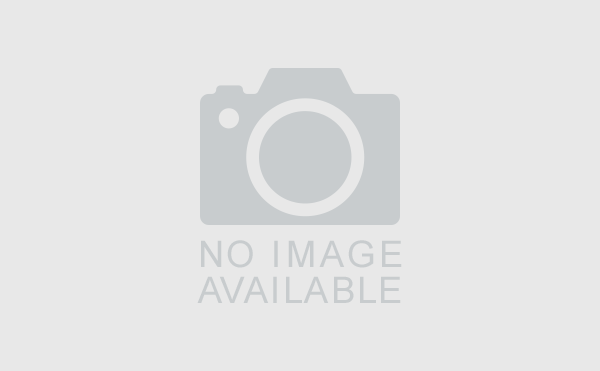認知症の親の遠距離介護について

一緒に生活していないと、認知症の親の実際の状況は分かりません。
母が認知症になった当初は、母の近くに住む親戚から
「様子がおかしいから何とかしろ」だの、
母が良かれと思って病院へお見舞いに日参するのを、
「同じことばかりずっとしゃべっているから、こっちはストレスだ」だの、
自分が預かり知らないところで母が起こしているトラブルを聞いたり、
対処するのはつらいことでした。
私が仕事中だろうが何だろうが、時間に関係なくそうした連絡を
よこす人もいましたし。
母と血の繋がりがある親戚でも、面倒見るのは子どもの役目だというのが
一般的な認識なんだと知りました。
母に毎日電話して様子を尋ね、その内容に当初は安心していましたが、
”子どもに心配をかけたくない”という気持ちと、親として、人間としての
プライドを守りたいためか、現状を取り繕い、母自身が理想とするような
生活をしているという、大半が嘘の話をされていたことに、
しばらくしてから気づきました。
これまで知っていた母ではなくなっていくことへの葛藤は、
母が亡くなるまで続きました。
実際に母の家に帰ってみると、電話での話と生活実態が
ずいぶんかけ離れていました。
ゴミの分別や収集日の把握が難しいので、ゴミが溜まっている。
生ゴミは捨てたいのに捨てられないので、冷蔵庫に保管してある。
「毎日料理して、野菜をいっぱい食べている」と言っていたのに、
料理ができる状態ではなく、スーパーでパンやお惣菜を買って食べている。
美容室に行けなくなって身だしなみが整えられない。
認知症の薬が自分では飲めなくて、大量に残っている。
トイレットペーパーやティッシュが一生かけても使いきれないほど
買ってある。
など、想像できないような状況をよく目にしました。
手軽だし昔から好きだったためか、パンを好んでよく食べていましたが、
認知症悪化要因はパンとか糖質が餌なのかな、と思ったりしていました。
栄養管理や身だしなみ、薬の服用など、日常の細々としたサポートが
必要になるので、認知症の親の遠距離介護は難しいです。
一緒に暮らしていても、自分の生活もあるし、
介護にすべての時間を使えるわけでもないので、遠距離でも同居でも、
無理をしないで、自分のできる範囲で介護に関わることが大切だと
思います。
プロではないから完璧な介護なんてできないし、”目を背けることなく、
介護に関わっているだけで偉い”、と自分を労わることも大事です。