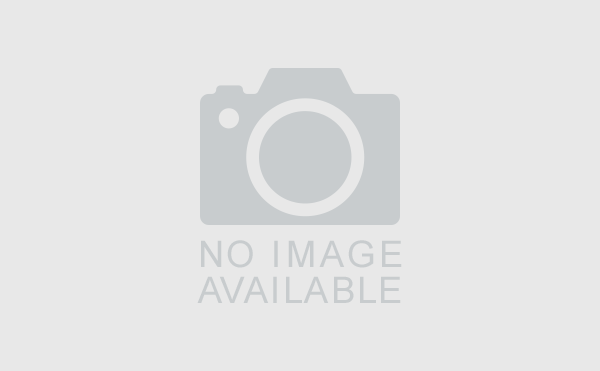子どもの食の好みは変化する

昨日のブログ「そんなに心配しなくても大丈夫」にも通じることですが、
子どもの食の好みは成長するにつれて変化するので、今好き嫌いのことで
悩んでいても、長い目で見るのが大切だと思います。
食べないとイライラすることもありますけれど・・。
私自身、子どもが小さいうちは子どもの食事についてかなり気を遣い、
エネルギーを使っていました。
特に第一子は全てが初めてなので”体に良いものを食べさせなきゃ”と考え、
離乳食が始まった頃なんて出汁から何からすべて手作りじゃないといけないような
凝り固まった考えに囚われていて、時間的にも精神的にも余裕のない中、
せっせと子どもの食事を作っていました。
この頃は”この子は私が与えるものでできているんだ”というような
妙な満足感というか高揚感みたいなものもあったな。
疲れすぎていたのかも。
普通の食事ができるようになると好き嫌いなくなんでも食べて欲しいと思って
調理法を工夫したり、子どもが嫌がっているのに粘り強く食べさせてみたり、
食事についてはかなり神経質になっていたと思います。
食べない物があると落ち込んだし、将来健康に暮らしていけるのかしらと悩んだり、
目の前の問題が永遠に続くように感じていました。
でも、
子供が大きくなるにつれて家族以外との食事の機会も増えてくると、
これまで食べたことのない味に挑戦する気にもなり、
味覚も変化していくので、
子どもたちが大人になった今、
”えーこんな物も食べるようになったの?”なんてたまに驚いたり、
小さい頃に必死で食べさせようとしていた苦労は何だったんだ!と
拍子抜けすることもあります。
親が何でも食べていれば子どももそうなるだろうと思っていたけれど、
そういうわけでもなく、同じ物を食べて育ったはずなのに
上の子と下の子では好みも違うし。
やはり1人の人間としての個性なのかもしれません。
栄養バランスが取れた食習慣は大事ですが、
もっと長い目で見て良かったんだと今は思えます。
自分だって子どもの頃からこれまで食の好みは変わってきているけれど、
子どもの事になるとそんなことは忘れちゃうし。
手作りにこだわっても完璧な栄養が取れているわけではなかっただろうし、
あまり神経質にならずに楽しい食事の時間を増やせば良かった。
食事は楽しいもの、と子どもが日々感じるだけで良かったのかもしれないと
思います。
反省を込めて。