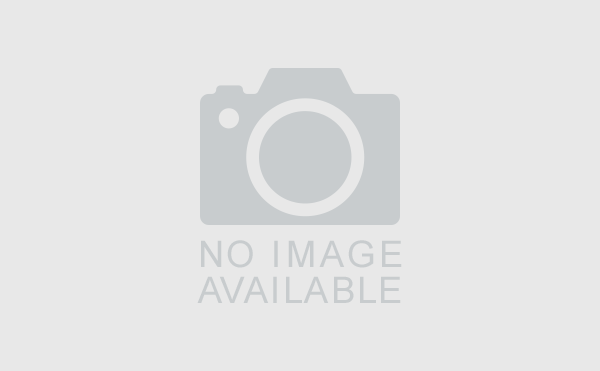『鴨川ランナー』(グレゴリー・ケズナジャット著)
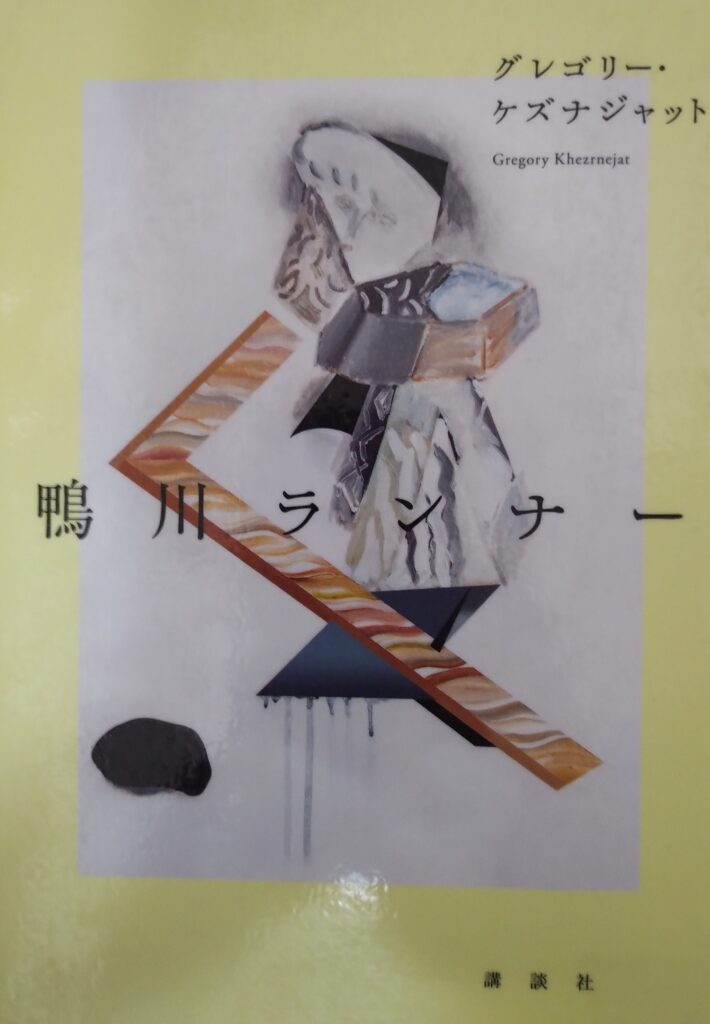
中篇2本が収められている中の1篇が『鴨川ランナー』。
著者のグレゴリー・ケズナジャットさんはアメリカ出身で、
第2言語の日本語で創作する作家さん。
少し前に読んだヤン・イーさんと通じるものがあります。
ヤン・イーさんの本の感想をこちらに書いています。
『エーゲ海に強がりな月が』(楊逸 ヤン・イー 著)
主人公は、日本語を学ぶ米国人青年の<きみ>。
<ぼく>じゃなくて<きみ>です。
高校時代に日本語を履修したことがきっかけで日本語に興味を持ち、
日本でいう修学旅行のような短期間の旅行で初めて京都を訪れ、
夕暮れの鴨川の美しさに魅了されます。
大学卒業後、英語指導助手として京都で暮らすことになりますが、
異文化の中でアイデンティティが揺らぐ様子や、日本人がどのように
見えるのか、などが描かれています。
母国語以外の言葉を机上で学ぶのと、その言葉が使われている異国に
観光ではない形で留まり、実際の生活の中で使うのとは
ずいぶん違うことに主人公は戸惑いますが、
気持ちが少しわかるような気がしました。
英語が母国語ならば、アルファベットを手がかりにしてヨーロッパ語圏では
少しは読める、何となく意味が想像できる単語などがあると思いますが、
英語と日本語ではそうした共通点が皆無。
以前アムステルダム駅に降り立った際、案内表記が全てオランダ語のみで、
「出口」という単語さえ探せず、この国から拒否されているような
気持ちになったことがありました。
困った時に助けになるような手がかりがないというのは、さぞかし
心細いことだと思えます。
そう考えると、欧米圏から来て日本社会で暮らす、逆に日本から行って
欧米社会で暮らすことは、双方容易なことではないのだとあらためて思います。
主人公は日本語を話したいのに、相手は気を遣って英語で話しかけてきたり、
思うように日本語が使えない状況も描かれていますが、
私も英語を使いそうな外国人だと見ると、相手が日本語で話しかけてきても
英語で返してみたり、お相手のバックグランドに合わせようとすることが
あります。
そうした気遣いは必要ないと感じる方がいて、もう少し想像力を働かせないと
いけない場面もあるのだと気づきました。
日本語の能力が高く、日本が好きで、自分は観光客ではなくて
日本の”住人”だという意識がありながら、どこまでも溶け込めないような感覚で
もがいているように見える主人公には、母国以外で暮らすことの難しさを
あらためて考えさせられました。